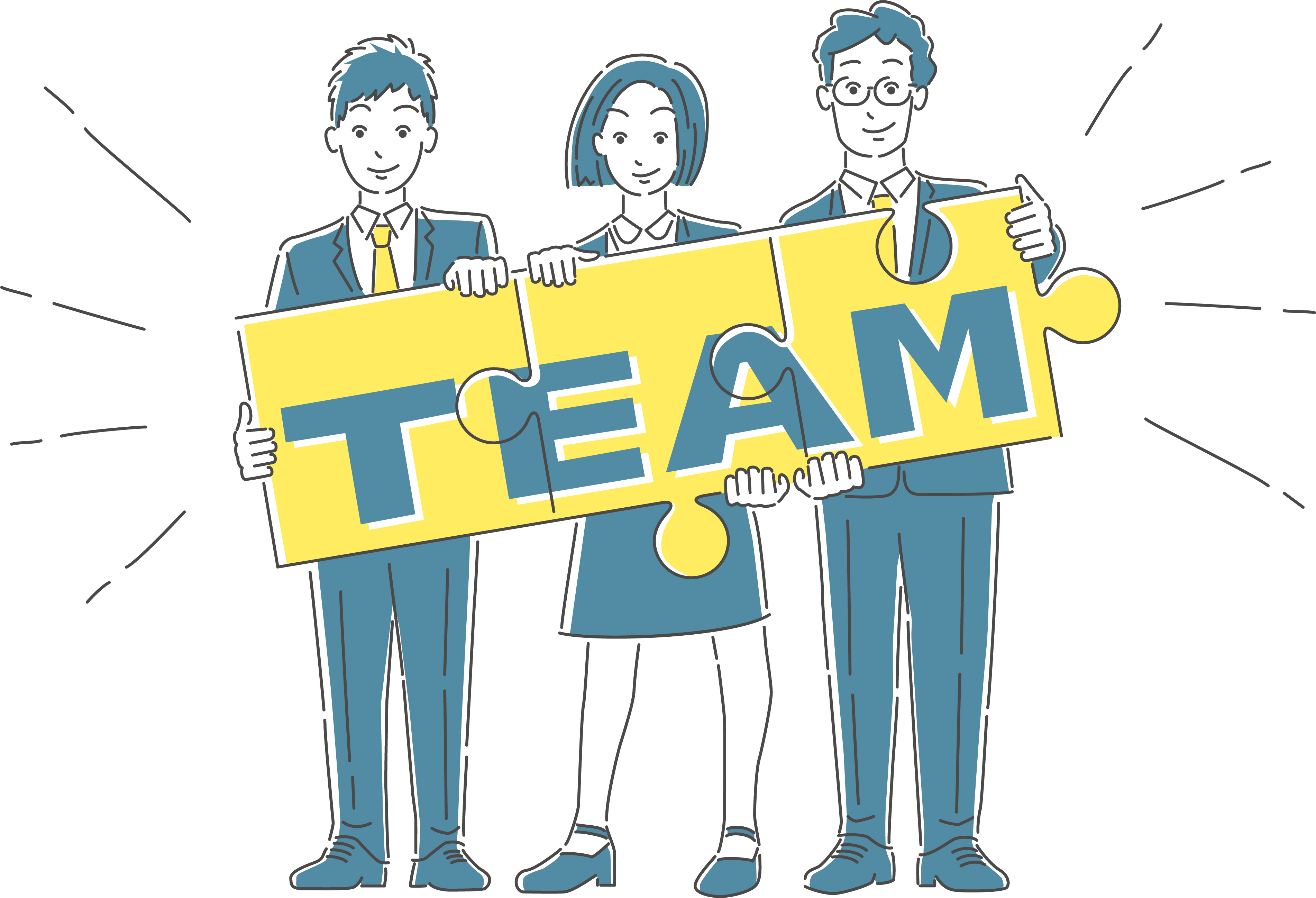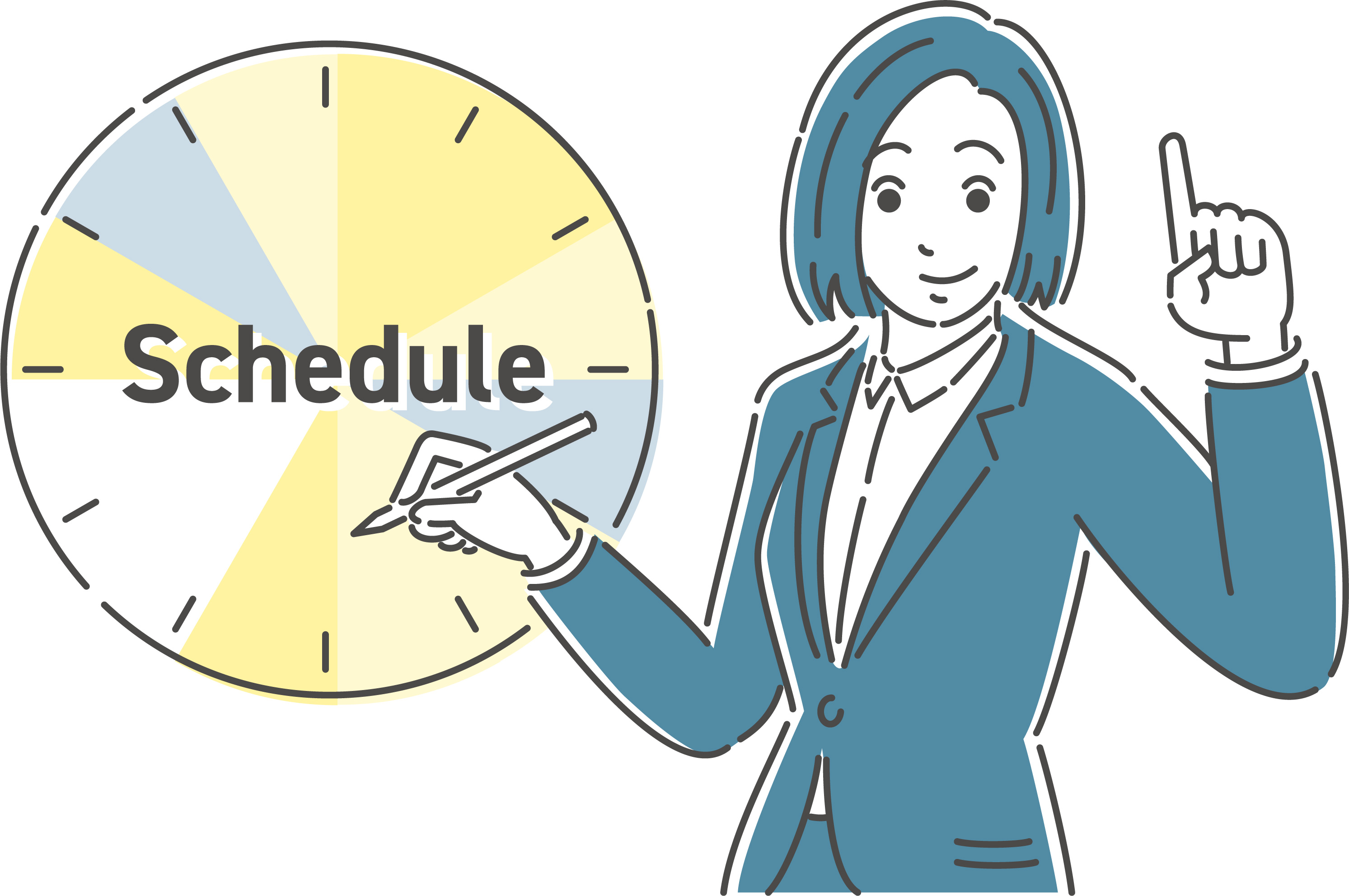感情の意味づけに寄り添うリーダーシップとは?

「大丈夫?」って聴かれると「大丈夫」って答えてしまうから、「どうしたの?」って声かけてみてね。
子ども運動スクールで、新人のコーチへ話したことを思い出します。
例えば、幼児によくある「大丈夫!」のケースは、“自分でやってみたい”という感情と、“いいとこ見せたい、褒められたい”という感情があり、そんな時は見守りつつ応援しつつ、「凄いね~できたね!助かるよ!」と声をかけると、得意げな顔で元気いっぱいになります。方や、年頃の中学生の「大丈夫」では、“ほっといてほしい”“皆の前で恥ずかしいから声掛けないで・・・”という感情が見えつつ、“話を聴いて”“どうしよう・・・”というもう一つの感情が見え隠れしている事が良くあります。そんな時は、「どうした?ちょっと向こうで話そうか?」と声をかけ隣に座り、その子が話をするまで待っていることがありました。
この事は、部下育成でも考えられる事かもしれません。部下育成を担うリーダーにとって、「感情への向き合い方」は避けて通れないテーマです。とくに、部下のモチベーションが下がっていたり、苛立ちや不安を抱えていたりする時、その“感情”をどう捉えるかで関係性もサポートの質も大きく変わります。だからこそ、部下が困難を乗り越えるカギとしての“感情理解”はとても大切なのかもしれません。
“感情”には「見える感情」と「見えない感情」があります。特に上司やリーダーが部下と向き合う時、この「見えない感情=二次感情」を理解する事が、育成や信頼関係づくりにおいて非常に重要なのではないでしょうか。
■感情には「一次」と「二次」がある
人の感情は大きく2つに分けられます。
一次感情:自然に湧き上がる、本能的な感情(例:悲しみ・怒り・不安)
二次感情:一次感情に思考や評価が加わって生まれる感情(例:恥ずかしさ・罪悪感・無力感)
たとえば、部下が叱られたときにムッとするのは「怒り(一次)」ですが、その裏に「悔しさ」や「恥ずかしさ(二次)」があるかもしれません。部下がふと見せた「怒り」や「落ち込み」を、そのままストレートに受け取って対応していませんか?
実は私たちが表に出す感情の多くは、「一次感情」に続いて表れる「二次感情」です。「一次感情」とは、出来事に対して瞬間的に湧き上がる素直な気持ち。たとえば、悲しい、寂しい、不安、うれしい、驚いたなど。それに対して「二次感情」は、あとから湧いてくる「反応的な感情」なのです。
■ 感情の奥には「意味づけ」がある
そして、人は、ただ出来事に反応しているのではなく、感情の背景にはその人なりの意味づけがあります。「それが自分にとって何を意味するのか」という解釈=意味づけを通じて感情を抱きます。
たとえば、ある部下がプレゼンでミスをした時、その時の反応は人によって違います。「悔しい。次は頑張りたい」「もうダメだ、信頼を失った」「上司にガッカリされたに違いない」など、この違いを生むのが、その人なりの意味づけです。つまり、同じ状況に対しても、「どう捉えたか」によって感情が変わるのです。
だからこそ、怒りや不満、沈黙といった“わかりづらい反応”の奥にある意味づけに気づくことができれば、リーダーとしてのアプローチはぐっと深く、温かいものになるのではないでしょうか。そして、表面的な感情に振り回されるのではなく、その人の感情の背景を知ろうとする姿勢が、部下の回復力や成長を支える土台となるかもしれません。
また、「二次感情」を知るうえで、勝手な決めつけには注意が必要です。人の感情は人それぞれで、とても個別的なのです。「きっとこう思っているに違いない」という決めつけは、信頼関係を損ねかねません。むしろ、わからないことに対して「知りたい」と思う姿勢こそが、相手の心を開く第一歩になるのです。
そして、その「二次感情」はなかなか姿を見せないことが多いようです。部下「・・・・」と考え内省している時は、ゆっくり待ってあげる事も必要かもしれません。沈黙も歓迎しながら、安心して話せる関係を育てていきましょう!
感情は、人の価値観や人生経験がにじみ出る、まさに“心の地図”のようなものです。リーダーがその地図に敬意を持って向き合うことで、部下との信頼は深まり、育成の時間が“対話を通じた成長の場”へと変わっていきます。
怒りの奥にある“何か”を知ろうとすることは、関係性を育み、困難を越えるカギを一緒に探す旅の始まりなのかもしれません。部下がどのような景色を見ているのか?見たいのか?一緒に探していきましょう!
<職場でのお困りごとなど、お問い合わせはこちらまで・・・>