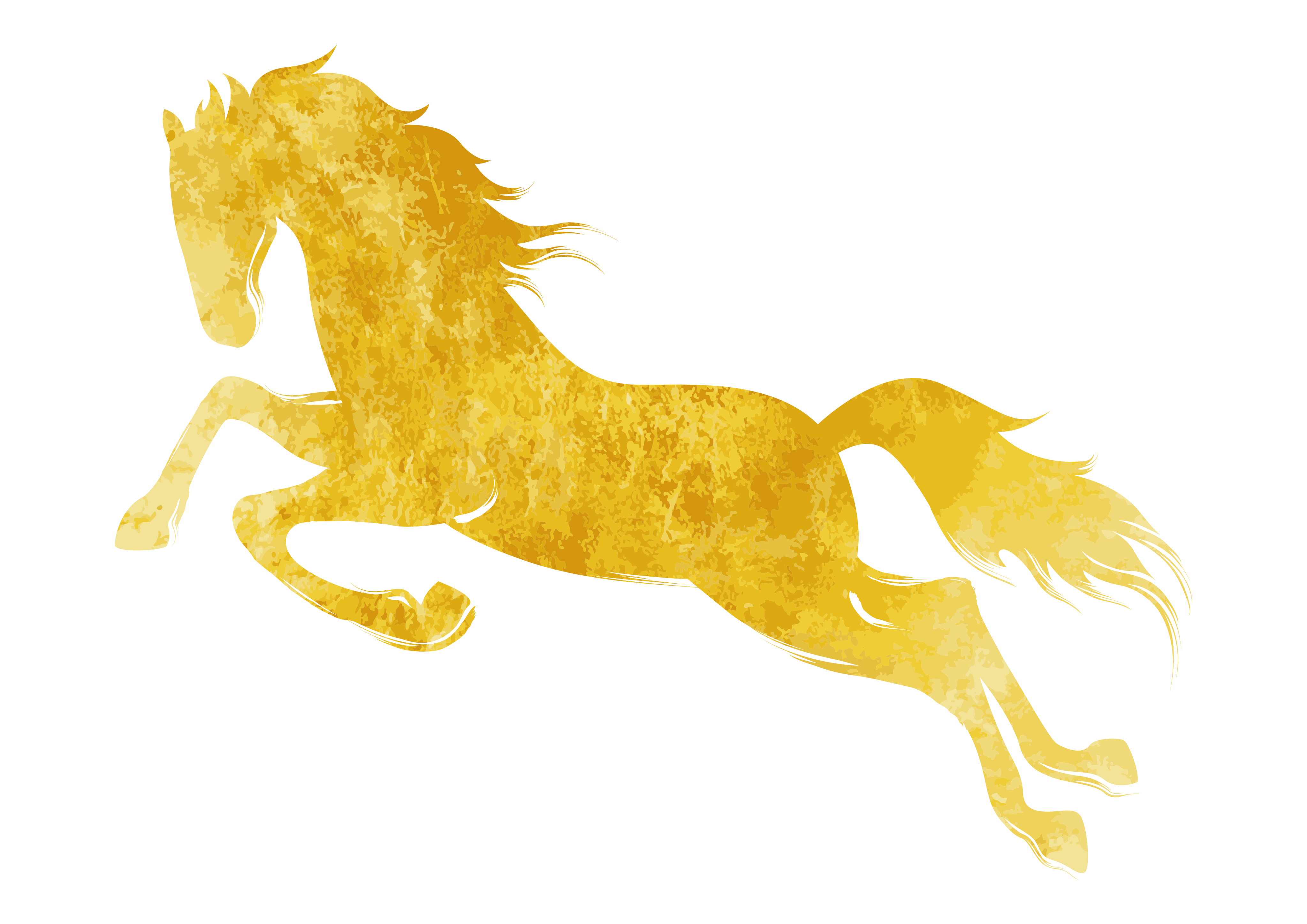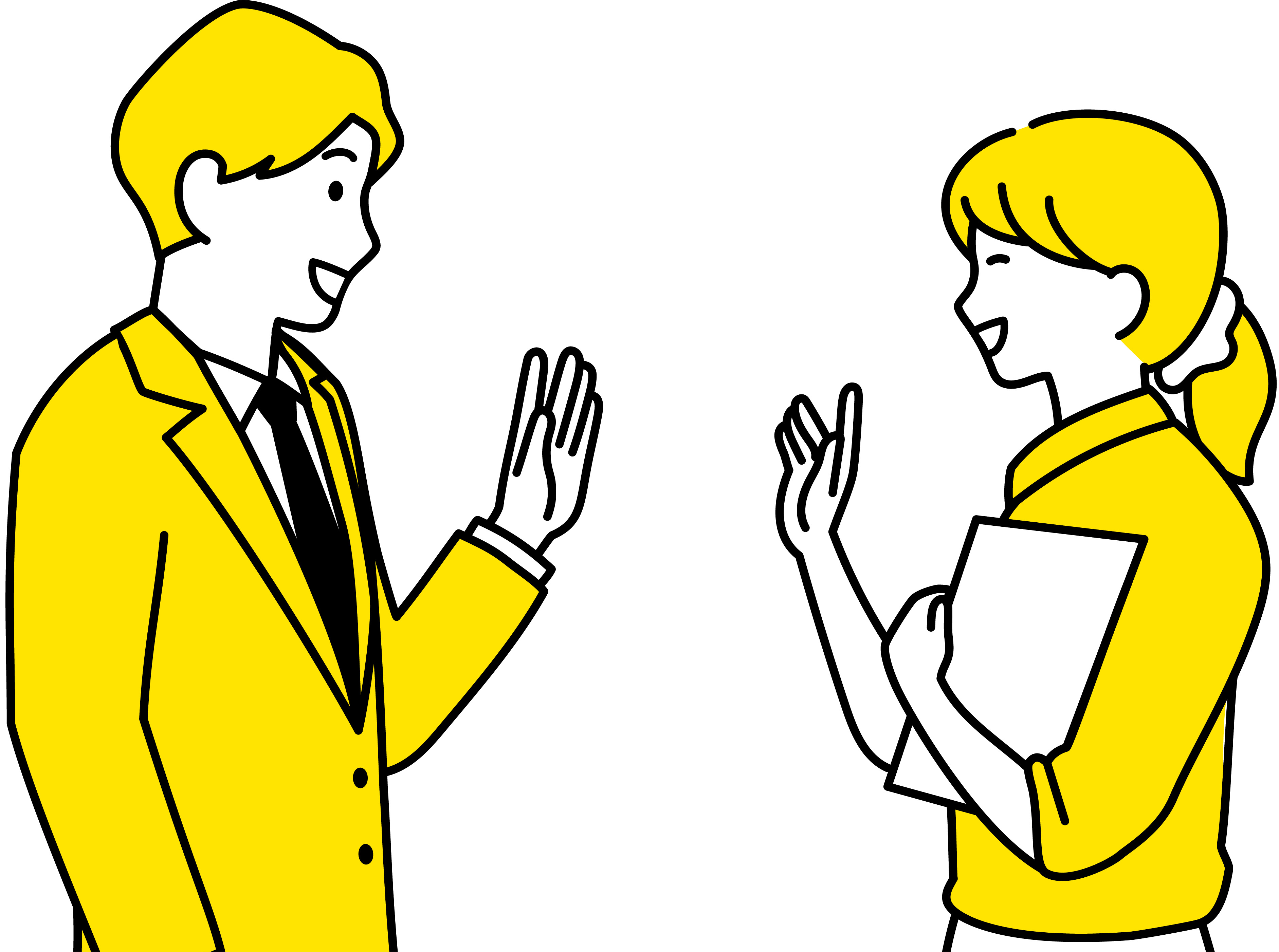若手に必要な働きかけとは?

「最近の若手は、自分から相談してこない」
「何を考えているのかわからない」
そんな声を現場で耳にすることがあります。一方で、若手社員の側も、
「何をどこまで言っていいかわからない」
「相談しても受け入れてもらえるかわからない」
といった不安を抱え、行動に移せずにいることが少なくないのではないでしょうか。今の若手世代は、丁寧に育てられ、周囲に迷惑をかけないよう配慮しながら育ってきた人も多く、慎重で空気を読みすぎる傾向があるとも言われます。そのため、「様子を見ているうちにタイミングを逃した」「自分の考えがまとまらず黙ってしまった」ということが起きやすいのかもしれません。
こうした若手に対して、ただ「もっと自分から来なさい」と求めるのではなく、相談できる関係性や、言葉を引き出す働きかけを意識することが、育成において重要なポイントとなるのではないでしょうか。
若手の相談行動を妨げる3つの壁
若手社員が相談をためらう背景には、“見えない壁”があると考えられています。
■心理的ハードルの高さ→ 怒られるのではないか、できないと思われるのではないか、という不安。
■相談のスキル不足→ 何をどう聞いたらいいかわからず、結果的に黙ってしまう。
■職場の空気・雰囲気→ 上司や先輩が忙しそう・怖そう・関心なさそうに見えることで、声をかけにくくなる。
このような壁を崩していくには、「質問していい!」「対話しても大丈夫!」という“安心感”が欠かせません。そしてそのためには、「何かあれば言ってね」という受け身の姿勢ではなく、具体的な働きかけが必要なのです。たとえば、
「最近どう?困ってることある?」と小さな声かけを日常的に行う
「この部分、どう考えて進めてる?」と考えを言語化させる質問をする
「話を聴かせて」と興味をもって声をかけることで、“話してもいい”という許可を相手に与える
相談を受けたときは、すぐに評価・アドバイスをせず、まずは最後まで聴く姿勢を大切にするこれらの関わりによって、若手は「聞いてもいい」「話しても否定されない」と感じられるようになるのではないでしょうか。
逆に、話し始めた瞬間にアドバイスをされたり、「それは違うよ」と遮られる経験をすると、「やっぱり話さないほうがいい」と学習してしまうのです。その学習が重なると、心を閉ざすだけでなく、考えることを放棄し何でも判断を委ね、指示待ち人間になってしまいます。
“話す”という行動は、相手に心を少し開く行為
その最初の一歩を引き出すには、「まず話してもらう」「それを丁寧に聴く」ことが、促す働きかけの基本になります。育成の場で大切なのは、すぐに答えを与えることではなく、考える力を育てることです。若手の考えがまとまりきっていなくても、「まずは話してごらん」と受け止め、対話を通じて整理させていくことが、結果的に自律性を引き出し、これからにも繋がります。
「どうしたらいいかわからない」と言ってきたときに、「どうなりたいと思っている?」と問い返す
「うまくいかなくて…」という声に、「どこで詰まったのか、一緒に見てみよう」と伴走する
こうした対話を通じて、若手自身が自分の思考を“言葉にして整理する”ことができるようになります。これは、単なる業務の指導ではなく、キャリア形成の土台を育てる支援でもあるのです。
指導ではなく、信頼ベースの関係づくりを!
働きかけのベースにあるべきは、「育ててあげる」ではなく「信じて関わる」姿勢なのではないでしょうか。若手にとって、上司や先輩がどう関わってくれるかは、その後の行動や思考スタイルに大きな影響を与えます。
失敗しても大丈夫と伝える・話を遮らず、最後まで聴く・小さな変化や成長を見逃さず、言葉にして伝える
このような関わりが、若手にとって「この人には話してもいい」「この職場なら安心できる」という実感につながり、相談やチャレンジが増えていくのです。
若手社員が自ら考え、相談し、行動できるようになるには、「成長の土台」を支える関わりが欠かせません。答えを与えるより、引き出す。評価するより、理解しようとする。その一つひとつが、これからの育成に求められる“プロの関わり”ではないでしょうか。
若手を変える前に、まずは自分の関わり方を変えてみませんか?
その一歩が、職場に対話と信頼を育む土壌をつくっていくのではないでしょうか。