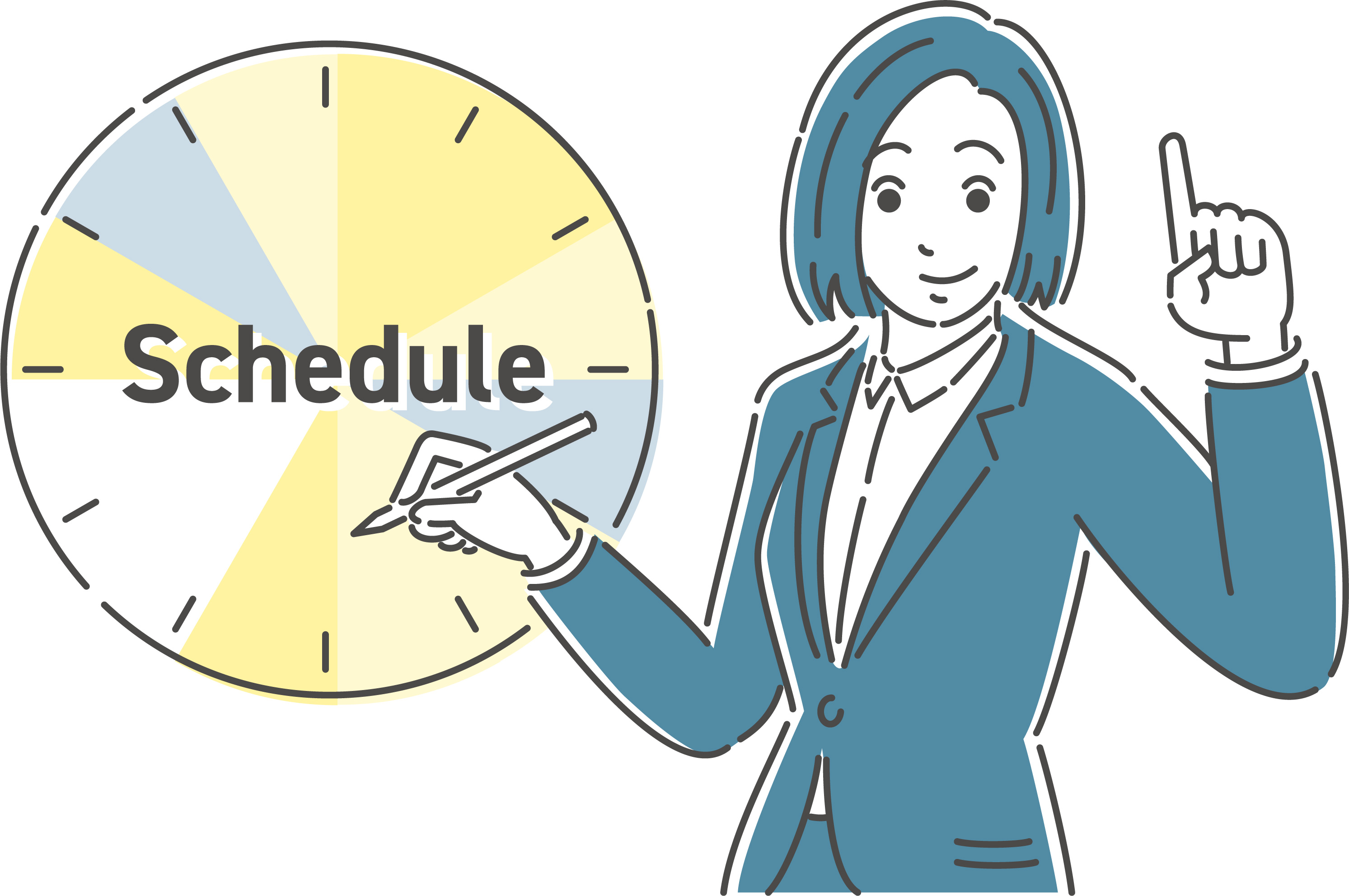個人と組織の志が響き合う方法とは?

仕事、志事、士事、支事・・・「しごと」とよむ漢字は色々ありますが、皆さんはどう捉えていますか?
私たちは日々「仕事(しごと)」をしています。しかし同じ「しごと」でも、「仕事」と「志事」と書いたとき、その意味合いは大きく異なるのではないでしょうか。
「仕事」は生活の糧を得るため、組織の一員として与えられた役割や責任を果たすための行為を指します。一方「志事」は、自分の志を基盤にして取り組む行為。社会に貢献したい、誰かを支えたい、自分の価値観を活かしたい。そうした思いと結びついた働き方です。
キャリアコンサルタントの視点から見ると、この「志事」の考え方は、自分自身のキャリア形成を考える上でも、部下を育成する上でも大切な要素だと考えています。
自分のキャリア形成と「志事」
キャリアを歩む過程では、「何のために働いているのか?」が揺らぐ瞬間があります。
毎日のルーティンが作業化し、やりがいを感じにくい・・・
期待通りの成果が出ず、自信を失う・・・
周囲と比べて、自分の成長が停滞しているように感じる・・・
そんな時に立ち戻りたいのが「志」です。志は「自分は何を大切にして働きたいのか」という価値観の表れです。仕事内容や職場が変わっても、この軸があることでキャリアはぶれにくく、一貫性を保てるのではないでしょうか。
実際に相談支援の現場でも、「自分の志に気づいたことで、働く意味が再び見えてきた」という方は少なくありません。志を基盤にした「志事」として捉えることで、同じ業務でも「作業」から「誰かの役に立つ使命」へと変化し、モチベーションやレジリエンスを高めてくれるのです。「私はこのためにいる」と存在意義を感じる捉え方でもあります。
部下育成における「志事」
管理職やリーダーにとっても「志事」という視点は重要です。部下にとっての志は人それぞれであり、「お客様の笑顔」「スキルの習得」「チームで成果を出す」など多様です。だからこそ、上司の役割は、部下の志を引き出し、それを日々の業務と結びつけることではないでしょうか。例えば、
「この業務は〇〇さんの得意分野を活かせるね!」
「このプロジェクトはお客様に直接喜ばれる部分だね!」
「この一つ一つが〇〇さんの経験になるし、チームの力になるはずだよ!」
こうした声かけを通じて、部下の認識は「やらされる仕事」から「自分の志につながる志事」へと変わります。結果的にエンゲージメントが高まり、成長意欲が高まるかもしれません。
志を共有する難しさ
一方で、組織全体で「志事」という視点を共有することは、言葉ほど簡単ではないのかもしれません。
志は人それぞれ違う・・・誰かは「顧客満足」、誰かは「技術の追求」、誰かは「安定した生活」。志は多様であり、組織が一つにまとめようとすると押しつけになりかねません。
業務との接点が見えにくい・・・日々の業務は数字や納期に追われやすく、社員からすれば「自分の志」と「目の前の作業」がどうつながるのか分かりにくいのです。
心理的安全性の不足・・・自分の志を語るには勇気が必要です。「そんなこと言っても評価されない」と思えば、社員は本音を語らず、共有が掛け声で終わってしまいます。
このように、「志を共有する」とは単に同じ目標を掲げることではなく、多様性や環境の課題に向き合うことかもしれません。
志を共有するための工夫
だからこそ、難しさを前提としたうえで、組織が取り組める工夫もあるのではないでしょうか。
対話の場をつくる:1on1やチームミーティングで「自分がこの仕事で大切にしたいこと」を語り合う。正解探しではなく「互いを知る場」とする。
組織のミッションと個人の志を重ねる:企業のビジョンに対し「自分の志とここが重なる」と感じられる接点を探す。
小さな実践を承認する:お客様への丁寧な対応、仲間への自然なフォローなど、日常の中に表れる志を見逃さず承認する。
リーダーが自ら語る:管理職や経営層が「自分の志」を率直に伝えることが、社員が語る土壌をつくる。
こうした取り組みを積み重ねることで、組織の中で「個人の志」と「組織の志」が響き合う状態をつくることができるのではないでしょうか。
「仕事」を「志事」と捉えることは、自分自身のキャリア形成を考える指針となり、部下育成の支援にもつながります。ただし組織全体で志を共有するのは簡単ではなく、多様性や心理的安全性など現実的な壁もあります。
だからこそ、一人ひとりの志を尊重し合い、組織の方向性と重ね合わせていくプロセスが大切です。個人と組織の志が響き合うとき、「志事」に取り組む喜びは拡がり、働く人も組織も共に成長していくのではないでしょうか。
<職場のご相談やキャリアのご相談などお問い合わせはこちらまで・・・>