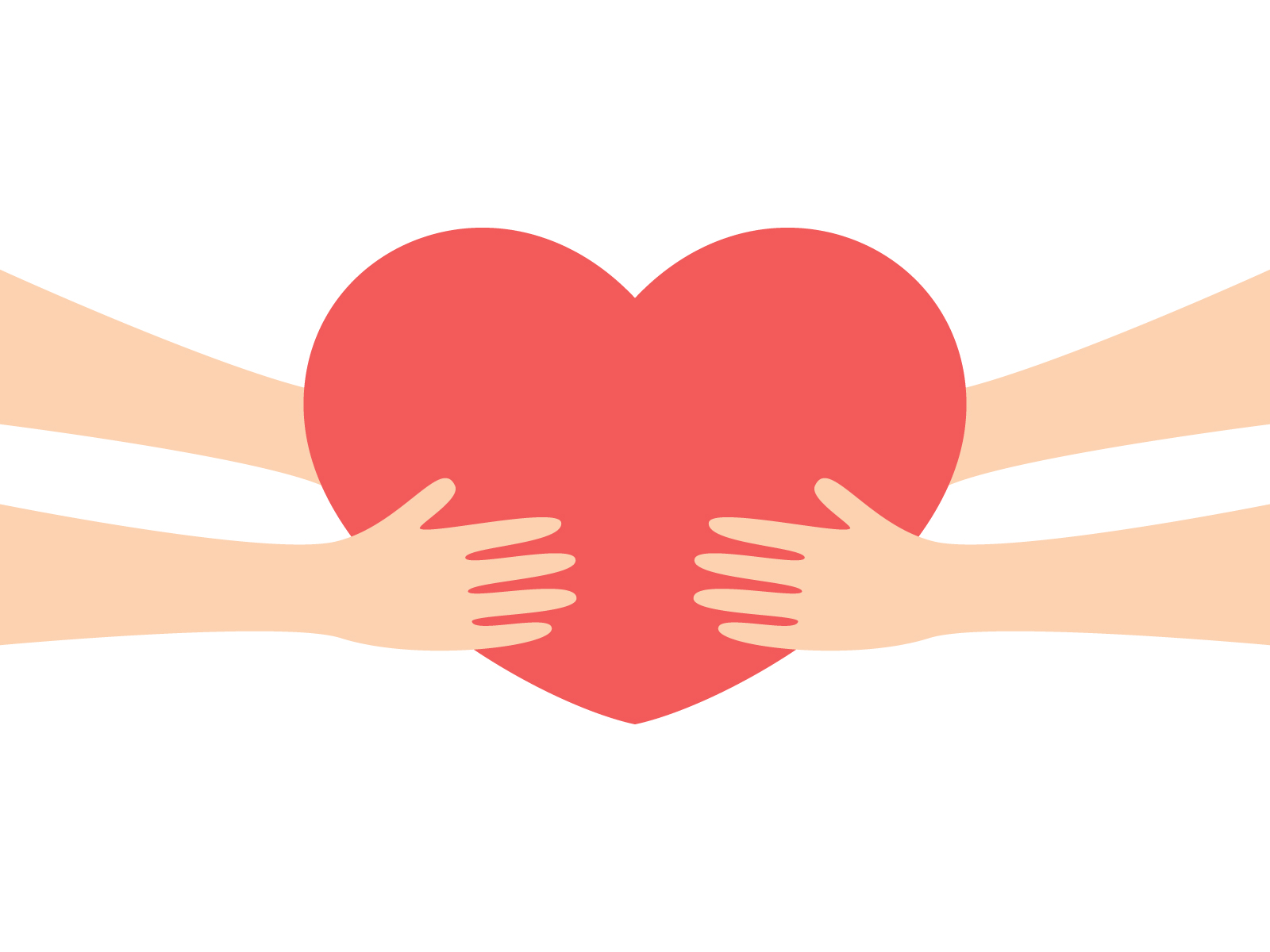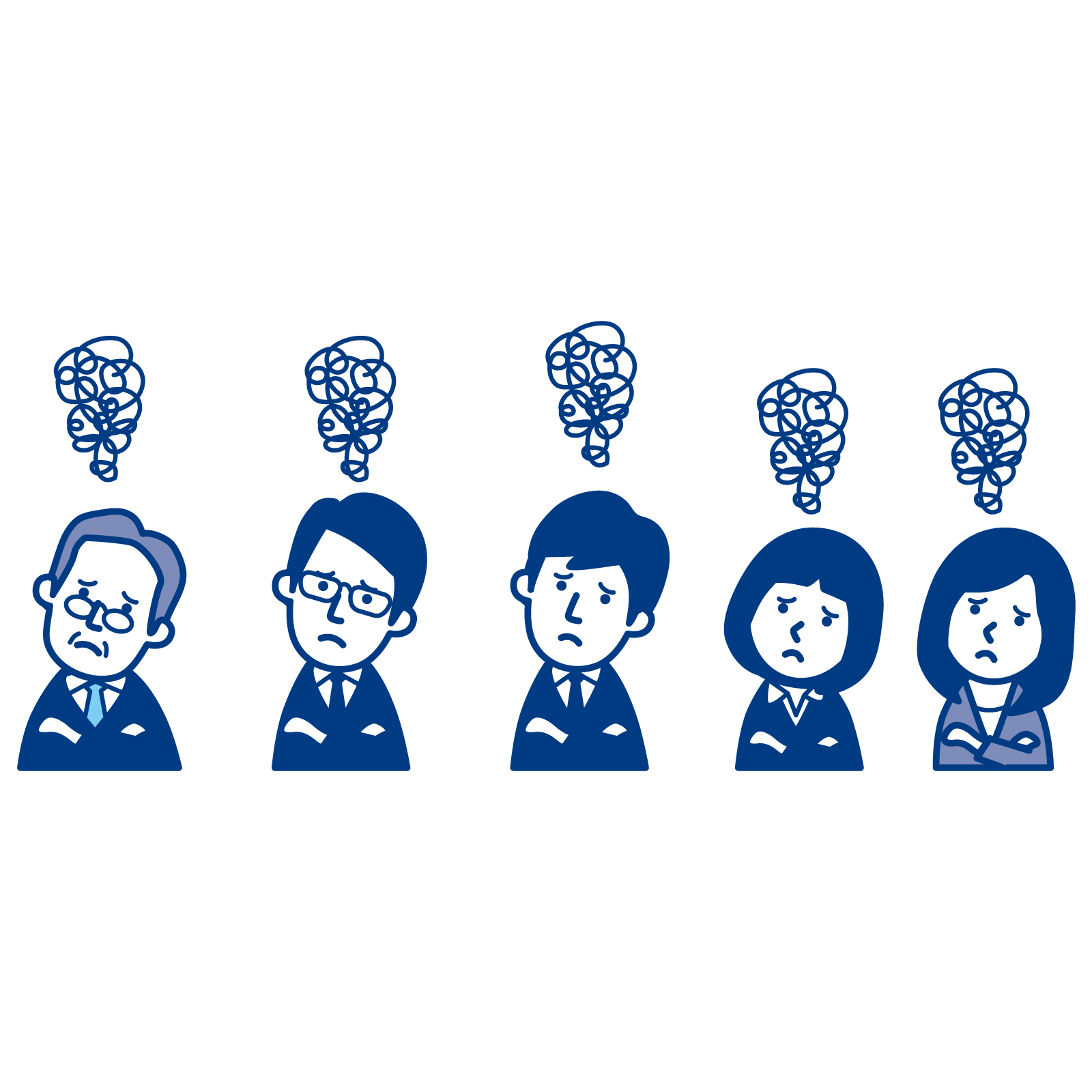話を聴いているつもりがいつの間にか“会話泥棒”に?

みなさん「会話泥棒」になっていませんか???
先日、ある場でふと違和感と虚無感を覚えるコミュニケーションがありました。その場にいた数名が話をしていたのですが、気づけば全てが一人の話題に染まり、周囲はただただそれを聴く構図になっていました。
笑いも相槌もあるのに、なぜか温度が低い・・・・
「なぜだろう?」と自分の感覚をたどってみると、そこにあったのは“会話泥棒”の構図だったのです。
「会話泥棒」とは?
”会話泥棒”とは、相手の話を途中で奪い、自分の話や意見にすり替えてしまう行為を指します。
たとえば誰かが「この前、京都に行ってね」と言うと、「あぁ、京都なら私も!」とすぐに自分のエピソードを語り出してしまう、という感じです。
本人は悪気なく、むしろ共感しているつもりかもしれません。しかし結果として、相手の話は途中で遮られ、主導権が奪われるのです。この“共感めいた奪い方”こそが、会話泥棒の厄介なところなのです。
では、なぜ人は会話を奪ってしまうのか?そこには、いくつかの心理が隠れているようです。
一つは「共感の皮をかぶった支配欲」。
「そうだよね~」とうなずいた後、「でも〇〇だよね」「私はこう思う」とすぐに続けてしまう。本人の中では“話を深めている”つもりでも、実際には自分の価値観で相手の世界を塗り替えているのです。相手は「共感された」と思った直後に、「やっぱりあなたの話か・・・」と感じ、心の距離が開いていくのではないでしょうか。
もう一つは、「安心を求める心理」。
相手の話を聴くことは、時に自分の価値観を揺さぶります。だから、人はつい「自分の知っている世界」に引き戻そうとするのかもしれません。「でもこう考えた方がいいよ」「それは〇〇だからね」という言葉は、相手を安心させるどころか、実は自分が不安を感じないための防衛反応である場合も多いのではないでしょうか。
そして厄介なのは、こうした会話泥棒が、悪意ではなく“善意”から生まれていることなのです。「励ましたい」「共感したい」「役に立ちたい」――その思いが強いほど、“つい”言葉を重ね、相手の話を“奪ってしまう”ことがあるのです。
しかし相手が求めているのは、必ずしも「答え」ではないのです。多くの場合、ただ「聴いてほしい」「わかってほしい」ということではないでしょうか。
そして、この構図は、上司と部下の関係にもよく見られます。
部下が相談を始めても、上司が「俺の若い頃もな・・・」「その場合はこうすべきだ!」と話し始めてしまうケースです。その場では会話が弾んでいるように見えても、部下の中には「話せなかった・・・」「受け止めてもらえなかった・・・」という虚無感が残ります。つまり、会話を奪うことは、成長の機会を奪うことにもつながるのかもしれません。
だからこそ、社会人としてのコミュニケーションに求められるのは、「話す力」よりも「聴く力」なのです。特に、相手の話を途中で奪わず、最後まで受け止める姿勢は信頼関係の礎になります。たとえば、
・相手の話が終わるまで待つ
・自分の意見を言う前に「そう感じたのはなぜ?」と尋ねる
・「わかる」よりも「聴かせて」と伝える
といった小さな工夫が、対話の質を大きく変えるかもしれません。
そして、会話泥棒をしないということは、単にマナーの問題ではないのです。
それは、相手の世界を尊重し、自分の世界を一歩引いて“余白を持つ”ことでもあります。自分の安心を守るために言葉を重ねるのではなく、相手の安心を育てるために沈黙に耐える。その沈黙の中にこそ、信頼や理解が生まれていくのではないでしょうか。
人と人とが響き合うコミュニケーションは、一方的な語りではなく、相互の世界が行き来する場に生まれます。社会人としての成熟とは、話す量ではなく、相手の世界をどれだけ受け止められるかで測られるのではないでしょうか。
<職場のご相談やキャリアのご相談などお問い合わせはこちらまで・・・>