“共有の時間”が、職場を変える
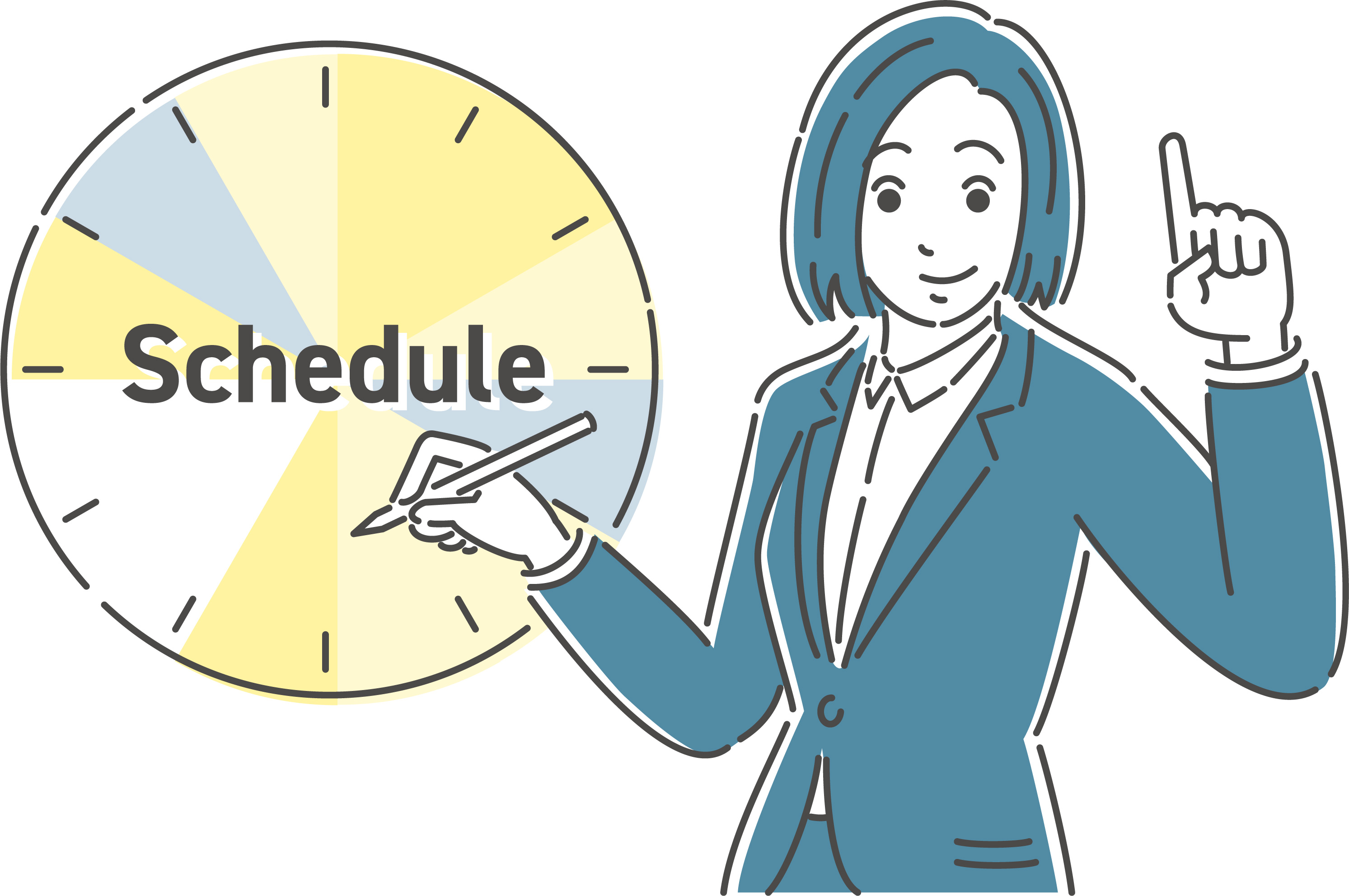
「毎週日曜日の〇時は家族でテレビを見る時間って決まってたよね!」
ある方との話の中で、子どもの頃の「時間の使い方」について話題になりました。
昔は「〇曜日の〇時にアニメを見たいから、それまでに宿題を終わらせる」「見終わったらお風呂に入って寝る」というように、テレビ番組の時間と自分の行動を組み合わせて考えることが、自然にできていたように思います。
また、「〇曜日の夜は家族でこの番組を見る」というように、家族みんなが一つの番組を見て笑ったり、涙したりする時間もありました。
しかし現代はどうでしょうか。
YouTubeや動画配信サービスの普及により、見たいときに見たい番組を、好きな場所で、しかも一人で楽しむことができる。便利で自由な反面、時間や人との関わり方に大きな変化が生まれていると感じています。
「時間に合わせる」から「時間を選ぶ」へ
かつては、テレビ番組の放送時間が「区切り」となり、行動にリズムがあったのではないでしょうか。「この時間までに終わらせよう」「ここからは休もう」といった、時間を意識した行動計画が生活の中で育っていたのかもしれません。つまり、限られた時間をどう使うかを考える「段取り力」や「切り替え力」が、自然と身についていたのではないでしょうか。
一方、現代は“いつでも見られる”環境です。
便利で自由な反面、「終わり」がないので、気づけば次の動画をクリックし、時間がドンドン溶けていってしまいます。「時間を選べる」ことが、いつの間にか「時間に流される」ことにもつながっているのかもしれません。
家族で過ごした“共有の時間”の価値
家族でテレビを見るというのは、単なる娯楽ではなく、一緒に笑う、驚く、感動する・・・その中で、感情を共有する力が育まれていたのではないでしょうか。
「あのシーン、面白かったね~」「あれはどう思った?」と会話を交わす時間が、家族の中での「他者理解」や「価値観の交流」を自然に促していたのかもしれません。
ですが、今は、家族それぞれが別の画面を見て、別々の世界で時間を過ごす。同じ屋根の下にいても、共有する時間や話題は少なくなり、“個の自由”を得た代わりに、“共に過ごす時間の希少さ”の時代とも言えるかもしれません。
そして、この“個の時間”が中心の感覚は、職場コミュニケーションにも表れています。ふと気づくと、昼休みや会議前、みんなスマホ画面に釘付けになっています。下を向いて、お互いの顔も見ず、話そうとせず、隣の人とは話せても、その場にいる人全体を巻き込み、場を温めるような会話はほとんど見られないようです。
情報は共有されていても、気持ちは共有されていない・・・
同じ空間にいても“つながっていない”感覚が漂う・・・
そこには「自分の時間を大事にする」価値観があり、悪いことではないのですが、行き過ぎると“共有の時間の価値”が見えなくなるかもしれません。
かつては職場でも、誰かが「この前見たドラマさ…」と話題をふり、その一言から雑談が生まれ、笑いが起こり、関係が柔らかくなる。そこには、共通の時間を持っていた世代ならではのコミュニケーション文化があったのではないでしょうか。
世代間の「時間感覚ギャップ」をどう越えるか?
年長世代は「時間を区切って計画的に使う」ことが身についているのですが、若い世代は「流れの中で柔軟に使う」傾向があるかもしれません。前者が「締め切りを守る」「余裕を持って準備する」を重視する一方、後者は「その時の感覚や流れ」を大切にする、という捉え方もあるのではないでしょうか。
どちらが正しいのか?という話ではなく、むしろ、それぞれが持つ時間の価値観の違いを理解し合うことが重要なのかもしれません。
「なぜ今、それを優先したのか?」「どんな時間の使い方を大切にしているのか?」そう問い合うことで、世代間の溝は対立から対話へと変わっていくのかもしれません。
では、リーダーにできることは何でしょうか?
リーダーや管理職の役割は、個の時間を尊重しながらも、共有の時間を意識的にデザインすることではないでしょうか。たとえば、
会議の冒頭に「最近印象に残ったこと」を1分ずつ話す
ランチミーティングや振り返りの場で“仕事以外”の話題を出す
進行のスピードよりも“空気の共有”を優先する時間をつくる
そんな小さな工夫が、「個」から「共」への橋渡しになるかもしれません。リーダーが「一緒に時間を過ごすことの価値」を信じ、場を整えることで、若手も次第に「共有の時間の意味」を体感し、職場の空気が変わっていくのではないでしょうか。
時間の使い方は、単なるスケジュール管理ではありません。それは、どんな人と、どんな関係を築いていきたいかという、生き方の表れでもあります。
スマホの中にも、個の時間にも、それぞれの価値があります。でも、誰かと過ごす時間、顔を上げて語り合う時間には、代えがたい意味があり、「時間の使い方」は「人との関わり方」なのではないでしょうか。
リーダーがその“共有の時間”を取り戻そうとする姿勢こそ、職場に温かさとつながりをもたらす第一歩なのではないでしょうか。
<職場のご相談やキャリアのご相談などお問い合わせはこちらまで・・・>


