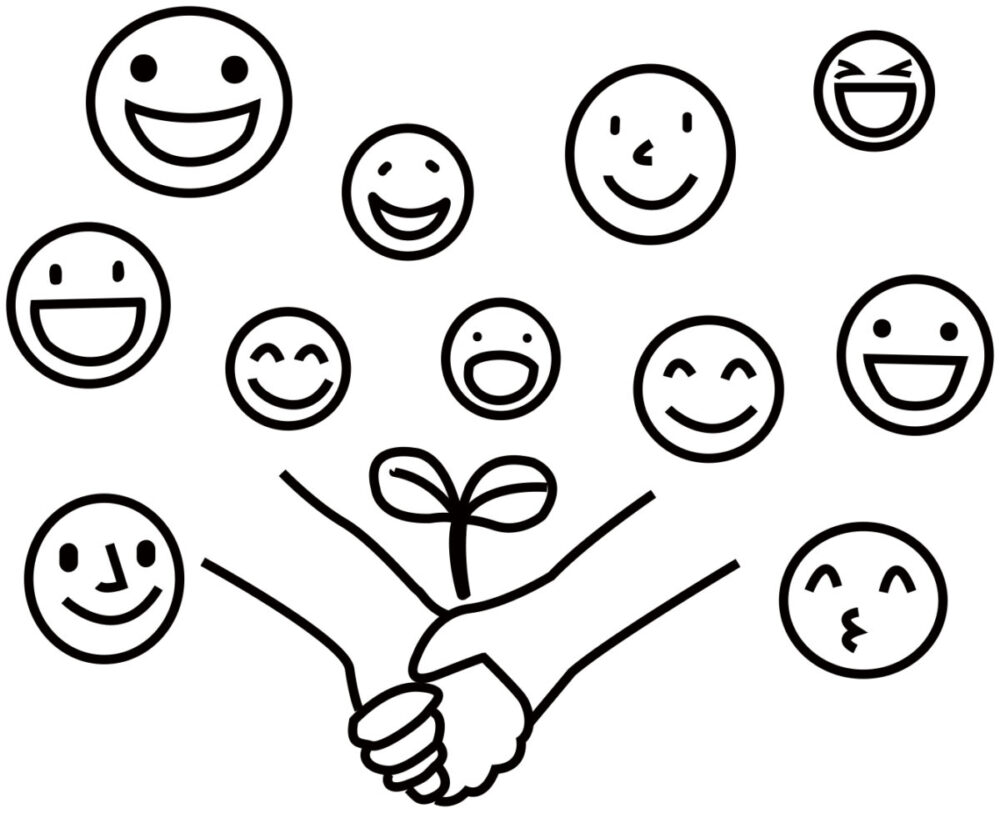やりたいこと VS やるべきこと??

「やっぱり主体性が必要だよね~」
人材採用の場面などで良く聴くワードではありますが、この「主体性」とは何なのでしょうか?
経済産業省が提唱した、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力を「社会人基礎力」と定義していて、3つの能力と12の能力要素があります。その能力の1つに「前に踏み出す力(アクション)」があり、その能力要素の1つに「主体性」があります。
「前に踏み出す力(アクション)」とは・・・
・一歩踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力
・指示待ちにならず、一人称で物事を捉え、自ら行動する
「主体性」とは・・・
社会人基礎力においては、「物事に進んで取り組む力」と定義されています。一般的には、自らの意思・判断で行動し自ら結果に責任を持つ姿勢や能力を意味しています。
特徴としては、「周囲から影響されて行動するのではなく、自ら目的と行動できる」「指示される前に、必要な行動ができる」などがあり、経済産業省の解説では、「変化に前向きに対処する力」「範囲を限定せずに主体的に動く力」という事もあるようです。
早朝のプロフェッショナルチーム
前職の話。ある支店で素敵なチームに出会いました。早朝から営業開始までの限られた時間で、施設内の清掃やメンテナンスを行うアメニティチームです。毎朝の清掃というとルーティーン作業のように思われますが、全くそれとは逆で、利用する人数や曜日・季節、施設のイベント、シフト状況などにより多種多様な形に変わるのです。自分達の基本ルーティーンは持ちつつ、その他要素に合わせて適応している姿は、まさに「自律型人材」であり、多くの学びがありました。
例えば、いつも(毎週)同じスタッフが同じ場所を担当しないという体制をとっていて、それは、同じ場所の清掃業務による身体の負担軽減はもちろんの事、他のスタッフが担当する事でより視点が広がり、細部に渡りきれいにできるという効果があるようです。同じ場所を担当した方が効率いいのでは?という見方もありますが、既にその体制での清掃ルーティーン経験は重ねられた後、各メンバーの技術が整ってきた為、週替わり体制になったのだと言われていました。実際、私も一時期担当した際は、まずは「同じ場所」の清掃を行い毎日鍛えられました。同じ場所だから見えてくる視点があり、その後、別の場所でその技術が活きてくるという、自分の成長実感と効力感を得ていました。
そして、「週替わりの場所を担当する事で気分も変わり楽しい!」と皆さん話されていて、働き続ける極意を教えていただいたように思います。
また、「清掃をする」のではなく、「施設を綺麗にすること」「綺麗な施設を気持ちよく使って欲しい」という思いがあると言われていました。その思いを形にし、色々な物事を自分事として捉え「自分が利用するんだったらどうかな?」「どうしたらもっと効率よく行えるのか?」と一歩踏み込んで業務に取り組まれている姿があったのです。その一つに、朝担当の方はお客様の利用はもちろんの事、営業中のスタッフが掃除しやすいよう道具を配置し、明日朝の自分達の為に準備するというルーティーンがあります。それは、当たり前のように感じますが、一つ一つが次の誰かの為に在り、それを今の自分達が行い、業務の良い循環を生み出していました。自分の周りにある様々な事を「自分ごととして捉えられる」というのは「主体性」の特徴でもあります。
そして、もう一つ強く感じたのは、各メンバーの責任感です。自分が引き受けた役割や行動に対して、最後までやり遂げる意識があり、例え困難があっても自分の選択に責任を持ち、結果に向き合う姿勢です。
この責任感は主体性との関係性があるのではないでしょうか?
主体性が強くても、責任感がなければ「やりたいことだけをやる」状態になりがちです。一方で、責任感が強くても主体性がなければ「言われたことをやるだけ」になってしまいます。だからこそ、「自ら考え、選択し、その結果に責任を持つこと」であり、主体性と責任感はセットで考えることで、より自律的で成長できる姿勢が生まれるのではないでしょうか。
社会人基礎力の12の能力要素の一つでもある「主体性」は、社会人として求められる機会が多い要素だと言われています。責任感とのバランスも大切ですね!
そして、各個人の能力を発揮しやすい「環境」という点も重要なのではないでしょうか。これから、新入社員や新配属者を迎える時期です。その環境要因には、私たち一人ひとりも含まれます。
「自分はどうかな???」
<職場のご相談やキャリアのご相談などお問い合わせはこちらまで・・・>